ドストエフスキー『地下室の記録』

ロシア文学者・亀山郁夫による
新訳『地下室の記録』
↓↓↓
著者は
言わずと知れたロシアの文豪
フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー(1821-1881)
↓↓↓
もともと
『地下室の手記』の題で
日本でも広く知られた
ドストエフスキーのキャリアの
中核をなす作品です
いやあ
僕も若い頃に度々読んでいますが
この新訳はまた
だいぶ印象が変わりますね
本書より
「まえがきにかえて」を転載
↓↓↓
地下室に住む中年男の告白を通じて、人間存在の矛盾と不条理に根ざした生の哲学を描く。
ドストエフスキー全作品を解く鍵と評される“永遠の青春の書”をロシア文学者・亀山郁夫氏による名訳で。
「この小説がドストエフスキー文学の原点です」―亀山郁夫。
「地下室」とは、言い換えるなら、青春時代を生きるだれもが一度はくぐりぬけなくてはならない“戦場”である…ドストエフスキーはこの人物を通して、ある一つの真実を語りかけようとした。
すなわち、この“戦場”を戦いぬくことなく、遠い将来、一個の自立した人間として大きな成熟を手にすることはできないということを。
この『記録』にこめられているのは、おそらく若いドストエフスキーが身をもって経験した躓きの記憶だが、その痛々しい記憶の彼方に輝いているものこそ、人間の真実、あるいは人間の生命という聖なるオーラなのである。
…となっています
あらためて
ドストエフスキーは
作家として身を立てて間もない若き頃に
空想社会主義に傾倒し
革命思想家ペトラシェフスキーのサークルに参加していたことから
1849年に官憲に逮捕され
死刑判決を受けます
そうして
銃殺刑執行直前のところで
特赦を受け
その後、シベリアに流刑
4年間の過酷な服役経験の後
1850年代に文壇に復帰します
しかしこの時
彼はもはや社会主義を否定し
進歩主義者と相対する側に立つ
保守派、民族派へと
転向を遂げていました
う〜ん
本書の『地下室の記録』は
そうした精神的、肉体的苦悩にあえいだ
ドストエフスキーの
自己否定に裏打ちされた
シニカルな姿勢
不条理な世界観が
色濃く反映された作品で
後に
『罪と罰』
『白痴』
『悪霊』
『カラマーゾフの兄弟』
へと至る
ドストエフスキー文学の集大成となる
4大長編の
いわば萌芽をなす
記念碑的な作品と言えましょうか
そんなわけで
本書ですが
主人公の“地下室人”が
20年間つとめてきた役所を退職し
『地下室の記録』を書き始める
という内容の二部構成となっていまして
とにかくまあ
全編くどいこと…
自意識過剰ゆえに
理屈っぽく
辛辣な皮肉をまじえ
卑屈で自虐的ですらある独白が
延々続きます
無教養
ひいては野性的なるものに
あからさまな反感を示しながら…
しかし
病的なまでの自意識に苛まれるうちに
いつしか理性
いわば合理主義を否定
自身が経てきた幾多の経験から
社会に蔓延する不条理を肯定し
自然の法則が生み出してきた
無為なあり方を
自ずと求めるようになります
おっと
ある種
マゾ的な傾向も示していて
理性に依らないあり方の
一端が垣間見れて興味深いですね
と
ここで少し長文ですが
本書より二箇所を
以下に抜粋
↓↓↓
第一部 地下室
「…それにしてもきみたちは、ノーマルで肯定的なものだけが、ひと口で言って、幸せな暮らしだけが、人間にとって有益だなどと、どうしてそうも頑固、勝ちほこったように主張できるのか?理性が、利益の判断に誤ることはないというわけか?もしかして人間が愛しているのは、幸せな暮らしだけではないかもしれないではないか?そう、同じくらい苦痛を愛しているかもしれないではないか?いや、苦痛もまた、人間にとって、幸せな暮らしと同じくらい有益かもしれないではないか?いや、人間は、時としておそろしいほど熱烈に苦痛を愛するものだーこれは偽りのない事実である。…善し悪しはともかく、ときおり何かをとことんぶち壊してみる、というのも、なかなか痛快なことではないか。だからといって、わたしはなにも苦痛の肩をもつわけでもないし、むろん、幸せな暮らしの肩をもつわけでもない。わたしが肩をもつのは…自分の気まぐれ、その気まぐれが、必要なときにわたしに保証されている状態である。…」
さらにこちら
↓↓↓
第二部 ぼたん雪にちなんで
「…どうかすると急に、連中が自分より一段上の人間に見えてくるときがあった。当時、わたしの場合、相手を軽蔑するにせよ、自分より格上と見るにせよ、なぜか、急にそんなふうな気持ちになるものである。教養もある、まともな人間なら、自分に限りなく厳しく接すことなく、ある場合には、自分を憎悪するぐらい軽蔑することなく、虚栄心をいだくことなどできないはずなのだ。ところがこのわたしときたら、相手を軽蔑するにせよ、格上と見るにせよ、どんな相手と顔を合わせても、ほとんどの場合、こちらから先に目を伏せてしまうのである。こんな実験も試みたことがある。つまり、現にむかいあっている相手の視線に最後まで耐えきれるかどうかを試してみたのだ。結果はいつもこちらかが先に目を伏せることになった。これには、気が変になるくらい苦しめられた。また、他人の目に滑稽と映ることを病的なくらい怖れていたので、何ごとにつけ外見にかかわる限り、ルーティーンというべきものを盲拝していた。世間のしきたりに嬉々としてしたがい、突飛なふるまいに出ることを心底から怖れていたのだ。しかしどうしてこのわたしに我慢しきれただろう?現代の教養人の名にふさわしく、わたしは病的と言えるくらい知能が発達していた。ところが、あの連中ときたら、そろいもそろって鈍感で、しかも、羊の群れみたいにおたがい同士似通っていた。…」
となっています
いやはや
屈折してるなぁ
このように本書は
地下室という
“陰”に閉じこもった主人公の
赤裸々な内面が
つらつらと綴られるわけですが
しかし
おぼろげに
自分もどこか思い当たる節があるなぁ
ふと
こうした
ひとり勝手に
負のスパイラルモードって
よくよく
若い時分にありがちだよなぁと
あらためて
感じるところ大ですね
というわけで
『地下室の記録』
いやあ
ドストエフスキーの
メランコリックな世界に浸るのも
たまにはいいものですね



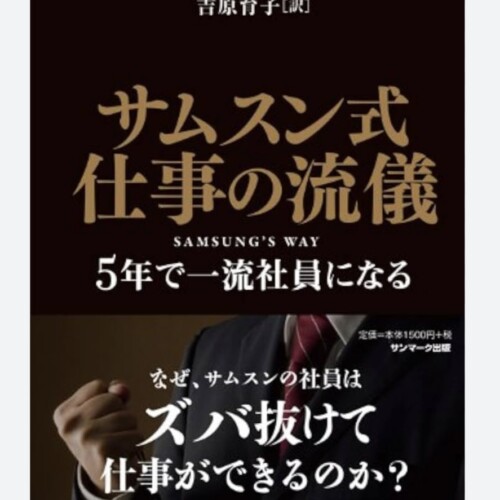

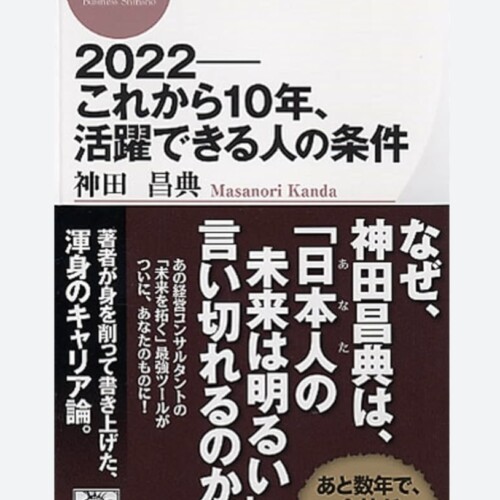
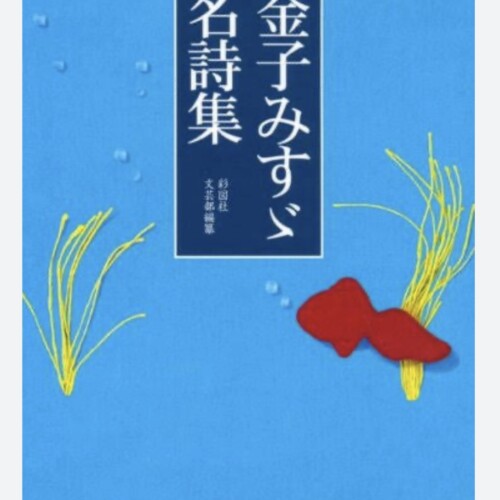


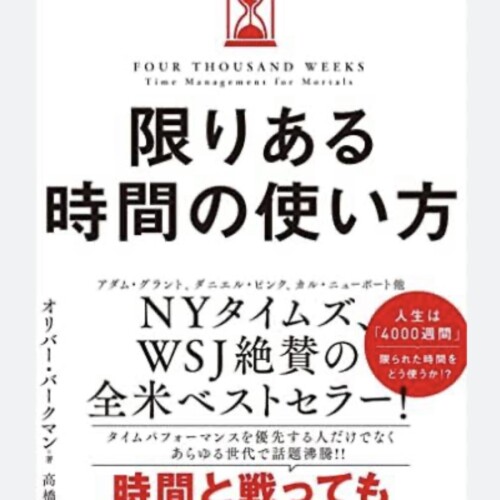
この記事へのコメントはありません。