映画『デッドマン・ウォーキング』

1995年製作のアメリカ映画
『デッドマン・ウォーキング』
↓↓↓
監督は個性派俳優として知られる
ティム・ロビンス(1958-)
↓↓↓
…
アメリカ、ニュー・オリンズ
アフリカ系アメリカ人の住む貧困地区で働く
カトリックのシスター・ヘレンは
ある日
若いカップルを惨殺した罪で服役している
死刑囚マシューからの手紙を受け取り
彼と接見することになる
当初は不遜な態度を示すマシューだったが
あくまで一人の人間として接するヘレンと
面会を重ねていく中で
二人は互いに心を通わせていく
↓↓↓
無実を主張するマシューの特赦を得ようと
ヘレンはひとり奔走するも
嘆願はことごとく却下され
まもなく死刑が確定
ヘレンは
マシューのスピリチュアルカウンセラーとして
執行日までの1週間を
彼に寄り添って過ごすことになり
そして…
↓↓↓
映画は
執行日を待つ死刑囚が抱く
不安定な内面をリアルに捉え
やがて罪を認め
神に許しを乞うに至る
内的葛藤のプロセスを
余すことなく映し出します
↓↓↓
あらためて
マシューがヘレンとの対話を通して
やがて心の内をさらけ出し
自ら悔い改めるシーンは
マシュー演じるショーン・ペンにとって
どれほどの精神的苦痛をもたらしたでしょうか
↓↓↓
何より
死刑囚の苦悩を受容し
本心を引き出す役割を担った
ヘレン演じるスーザン・サランドンとの
“魂”の交感を通して
高い集中力による
迫真のシーンが創出され
鉄格子を通した二人の濃密なやりとりに
観る者も自ずと没入していきます
↓↓↓
と
本作は
死刑廃止論者である修道女
ヘレン・プレジャンによる
ノン・フィクション作品の映画化で
死刑廃止を訴えたメッセージ性の強い作品
のようなイメージを持ちますが
果たして
監督の真意やいかに?
ロビンスはこの原作を題材にしながら
本作では
決して死刑廃止一辺倒の描き方をしていません
残虐な犯行シーンを挿入したり
被害者の家族の心情や置かれた状況などを
丁寧に描出することで
あくまで安易な結論を導き出さず
その是非を
どこまでも観る者に委ねるスタンスをとっています
↓↓↓
う〜ん
だからでしょうか
静かながらも熱量の高い
メソッド演技のショーン・ペンに
実のところ
感情移入しきれない自分がいます
どこかで
引いて見ている僕がいる…
↓↓↓
スーザン・サランドンも
真に迫ってはいますが
本質のところで
どこかカラッとしている
彼女自身の持つ
ある種の楽観性が
アメリカ南部の牧歌的な風景と相まって
独特のリアルなムードを醸し出しています
しかし
よくよく
それゆえに
本作のシリアスなテーマが
より鮮明に浮かび上がって来るのですが…
↓↓↓
つくづく
これは演出上
正しいアプローチで
お涙頂戴とか
ドロドロとしたトーンだと
逆に人為的な意図を感じて
おそらくは観ていてシラけちゃう
あくまでニュートラルな立ち位置を心がけて
終始淡々と対象に向き合う
そんなロビンス監督の姿勢と手腕には
いやあ
たしかな知性と誠実さを
感じずにはいられませんね
本作の終盤
家族と最期のひとときを過ごすマシュー
刻々と時間が過ぎていく
ある種、空虚なひととき
↓↓↓
ラストに近づくにつれ
観ていて
次第に
息が詰まりそうになります…
そうして
看守がおもむろに叫びます
「Dead Man Walking!」
タイトルとなったこのセリフは
死刑囚が死刑台に向かう際に
看守が呼ぶ言葉です
↓↓↓
ヘレンとのつかの間の交感を経て
関係者を前にして
最期に遺族に謝罪の言葉を述べ
死刑に対する廃止を訴えて
そして
マシューの死刑が執行されます
↓↓↓
本作は
死刑制度が持つ
決して晴れることのない問題
正義の意味
贖罪のあり方
倫理的な矛盾など
ありのままを提示することで
観る者に
その是非を問いかけます
と
余談ですが
本作に神父役で出演しているのが
リチャード・ブルックス監督の
『冷血』(1967)に主演した
スコット・ウィルソンで
この配役は
おそらくロビンスによる意図で
本作が
トルーマン・カポーティ原作の『冷血』に
インスパイアされている証左と
捉えて間違いなさそうですね
というわけで
『デッドマン・ウォーキング』
いやあ
見応え充分ですね
監督ティム・ロビンスの
的確な演出
主演のペンとサランドンの
絶妙な演技セッションが
見事な相乗効果をもたらした
まさに
秀逸な人間ドラマの力作です
↓↓↓







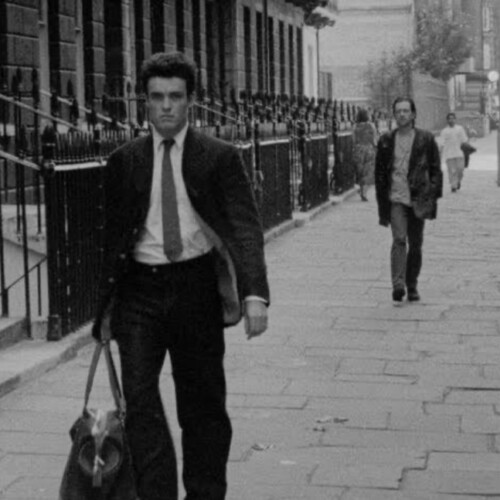


この記事へのコメントはありません。