『エゴン・シーレ展』

先日
合間を縫って行ってきました
ただいま
上野の東京都美術館にて開催中の
『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』
↓↓↓
世紀末のオーストリアに生まれ
わずか28歳で夭折した天才画家
エゴン・シーレ(1890-1918)
↓↓↓
本展は
ウィーンにおける芸術の爛熟期を
自身のアイデンティティを問う鮮烈な表現でもって
生き急ぐように駆け抜けた
この稀代の画家の全貌に迫る
またとない展覧会です
今回、メインとなる
ウィーンのレオポルド美術館の
所蔵作品を中心に
油彩画、ドローイングなど
シーレの作品50点が集結
短くも濃密な彼の生涯と創作の背景を
彼が残した言葉とともに振り返ります
またシーレのみならず
彼と同時代を生きた画家たち
クリムトやコロマン・モーザー、リヒャルト・ゲルストル、オスカー・ココシュカなど
の作品も併せて展示
いやあ
これは見逃せませんね
と
僕は今から約10数年前に
業界の関係で
ウィーンとブダペストへ
旅行に行ったことがありまして
ウィーンに行った時は
それはもう嬉しくて
美術館を何館もハシゴしたのを覚えています
しっかしウィーンというのは
街や建物のあちこちに
クリムトの作品などが点在したりしていて
つくづく美しい街で
クリムトの『接吻』も
直に観れて感激でしたね
そしてその際に
レオポルド美術館へも行きました
↓↓↓
白い端正な作りの素敵な美術館で
相当な数のシーレの作品を
それこそ浴びるように鑑賞しました
なので今回の『シーレ展』は
僕はほとんど一度観ていまして
中には忘れているものもありますが
大体覚えていましたね
ということで
本展の主要な作品をご紹介
◎《ほおずきの実のある自画像》(1912)
↓↓↓
シーレの代表作ですね
繊細なタッチ
鮮やかな色彩
不安定なフォルム
シーレの画家としてのある種の矜持…
う〜ん
小さな絵ですが
ほとばしる生がみなぎっています
◎《悲しみの女》(1912)
↓↓↓
独特の存在感があります
じっと見つめられているようで
つい引き込まれてしまいますね
◎《母と子》(1912)
↓↓↓
これも不思議な絵
激しい筆致
悲劇的な背景を持つ物語性を感じさせます
◎《自分を見つめる人Ⅱ(死と男)》(1911)
↓↓↓
覆うペシミズム
死の予感にとらわれた
画家の心の叫びのようです
◎《装飾的な背景の前に置かれた様式化された花》(1908)
↓↓↓
シーレには
正方形のカンヴァスや
背景に金銀を用いた作品が少なくないのですが
これは明らかにクリムトの影響が大で
装飾性、平面性を強調した
作風となっています
◎《菊》(1910)
↓↓↓
擬人化といいましょうか
悲しみをたたえたその風情に
思わず見入ってしまいます
◎《吹き荒れる風のなかの秋の木(冬の木)》(1912)
↓↓↓
これも面白い
渋い色調
風に震え
寂しく孤独な風情をたたえた細い枝…
特異な世界観を構築していますね
◎《モルダウ河畔のクルマウ(小さな街Ⅳ)》(1914)
↓↓↓
平面的で味わい深い色合いがいいですね
◎《頭を下げてひざまずく女》(1915)
↓↓↓
数多い女性像の中の一枚
エロティックで生々しい身体表現
刹那的なまでに悲壮感漂う筆致
◎《縞模様のドレスを着て座るエーディト・シーレ》(1915)
↓↓↓
斜め上からの構図を好んでいたシーレが
妻を描いた作品
上目遣いで不安気な表情ながら
穏やかな内面を感じさせます
さらに
他の画家の作品も充実
◎グスタフ・クリムト《シェーンブルン庭園風景》(1916)
↓↓↓
目を奪われるほどの美しさ
◎コロマン・モーザー《キンセンカ》(1909)
↓↓↓
彼は世紀末ウィーンを代表するデザイナーとして
名が知れていますね
◎リヒャルト・ゲルストル《半裸の自画像》(1902-04)
↓↓↓
シーレと並ぶ夭折の画家として
今回、確かな存在感を放っていましたね
シーレ以前にいた表現主義の画家として
今後、要注目となる予感大ですね
と
こちらのコーナーだけは写真OKでした
↓↓↓
豊かな線描
ドローイングの類稀な技術が際立ちます
↓↓↓
この人はかなりのナルシストだったんでしょうね
↓↓↓
多くの心に残る言葉を残しています
↓↓↓
いやあ
圧巻です
というわけで
生と死の狭間で
文字通り
己を刻み込んだエゴン・シーレの画業と
この時代の豊かな産物を堪能する
これはまたとない機会
是非オススメです


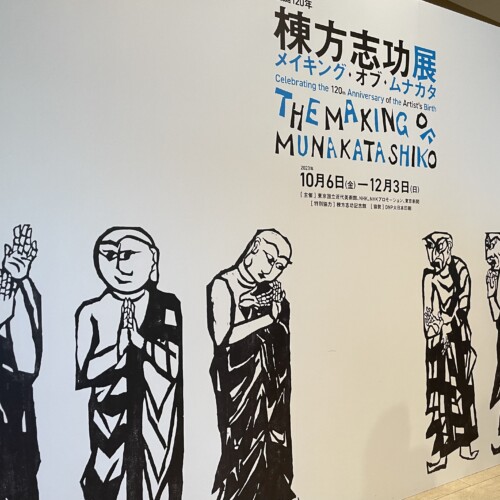

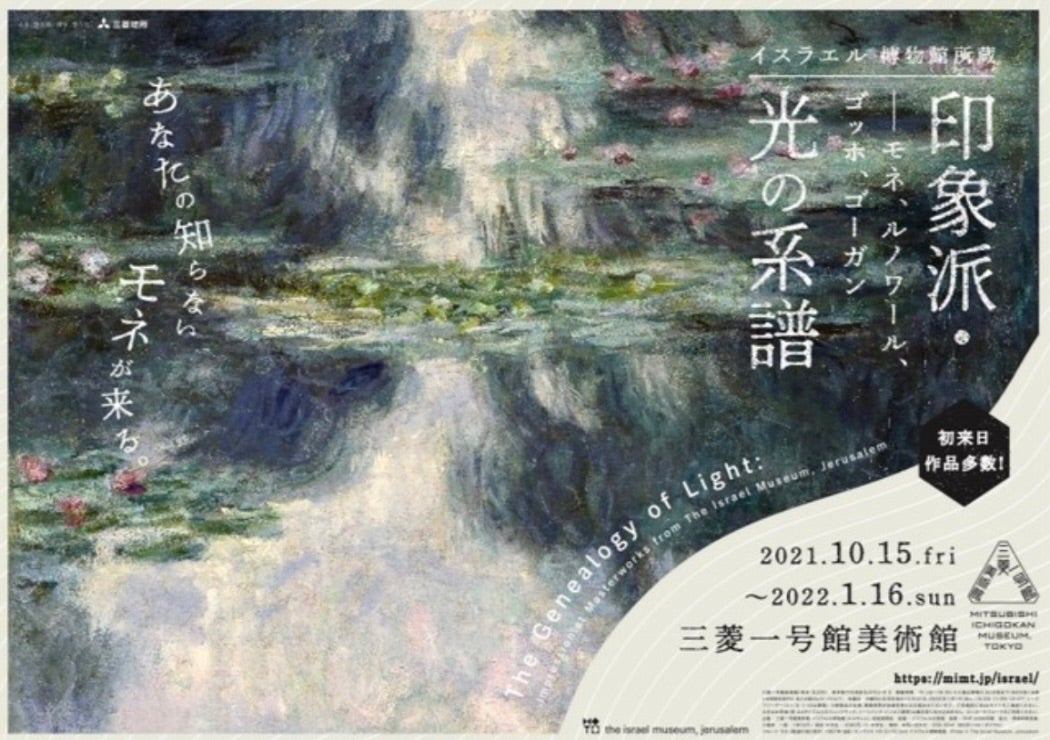
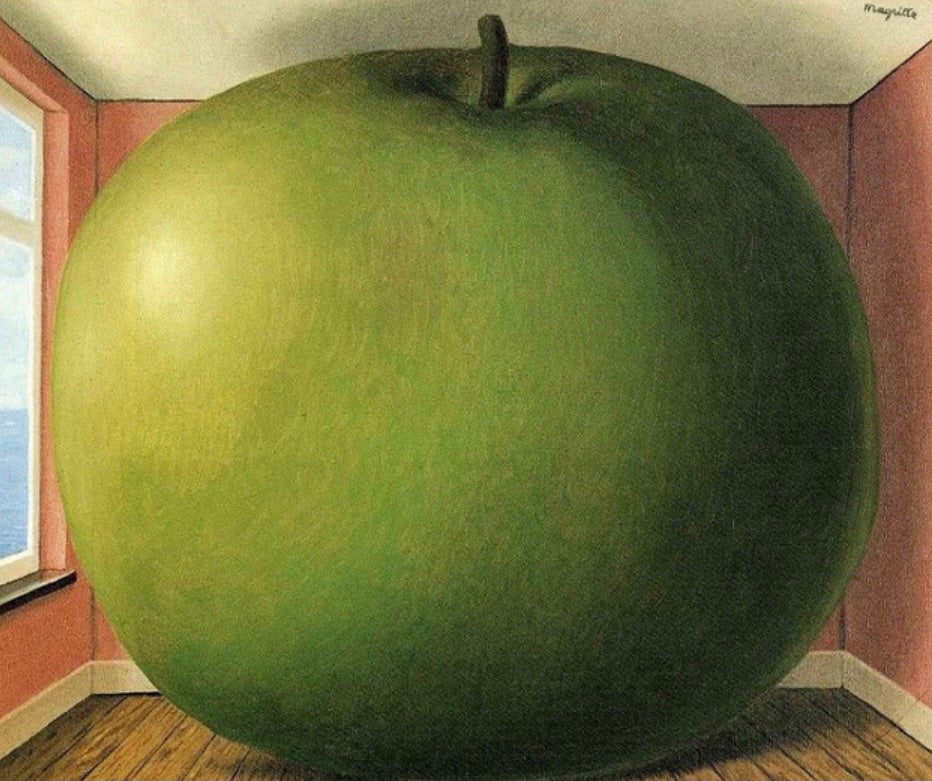

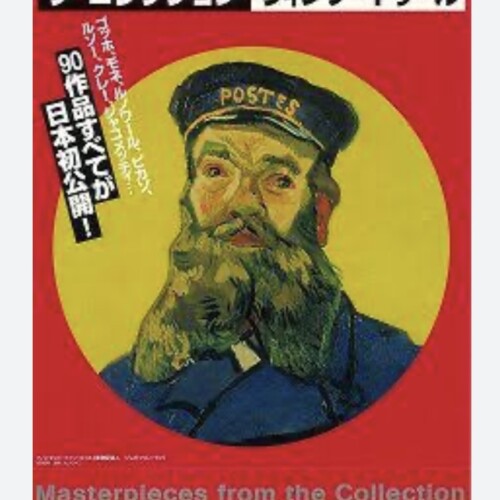


この記事へのコメントはありません。