有島武郎『生れ出づる悩み』
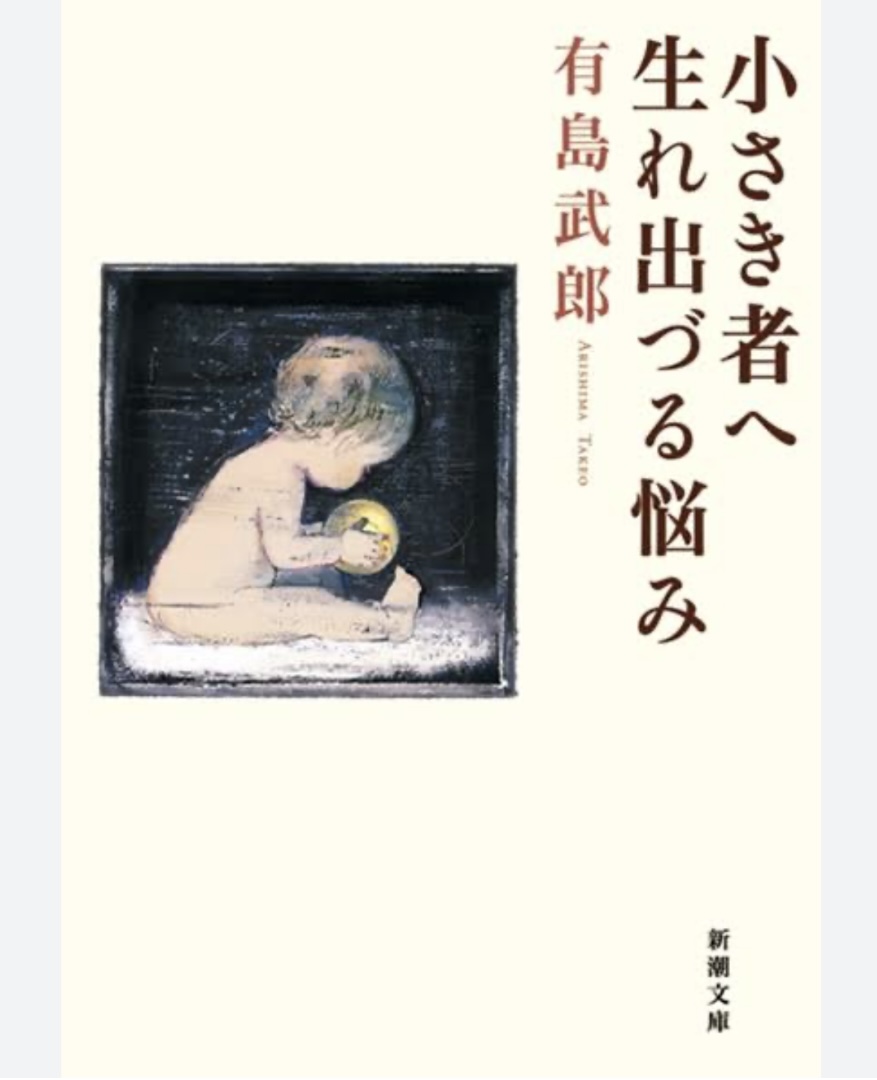
1918年(大正7年)に新聞に連載され
後に完成
明治から大正にかけて活躍した小説家
有島武郎(1878-1923)の
私小説といえる中篇
『生れ出づる悩み』
↓↓↓
こちらの文庫は
短篇『小さき者へ』と併せて刊行されています
本小説は
札幌で文学を志す”私”を
物語の語り手に
天賦の画才を持ち合わせながら
貧しさゆえに漁師としての生活を余儀なくする
あるひとりの友人を“君“と呼称し
漁業を営む”君”の過酷な日常と
そうした中でも
芸術への意欲を失わず
創作の炎を燃やし続ける様を
現実と理想
生活の刻苦と芸術への情熱が
激しく拮抗し合う様を
語り手の”私”が
想像を膨らませて綴っていきます
特には
精緻極まりないディテールによって紡がれる
北海道岩内の容赦ない自然環境と
漁師の厳しい生活風景を捉えた描写は
ただもうリアルで生々しく
その気迫の筆致には
ひたすら圧倒されるばかりです
そして己の芸術に対する思い
その苦悩する内面の
なんとまあ
切実なこと…
本小説における”君”のモデルは
有島とも親交のあった
北海道岩内の画家
木田金次郎(1893-1962)で
いやあ
興味深い限りですね
と
ここで心に残った箇所を
以下、転載
…
君は自分が絵に親しむ事を道楽だとは思っていない。いないどころか、君にとってはそれは、生活よりもさらに厳粛な仕事であるのだ。しかし自然と抱き合い、自然を絵の上に生かすという事は、君の住む所では君一人だけが知っている喜びであり悲しみであるのだ。ほかの人たちは―君の父上でも、兄妹でも、隣近所の人でも―ただ不思議な子供じみた戯れとよりそれを見ていないのだ。君の考えどおりをその人たちの頭の中にたんのうができるように打ちこむというのは思いも及ばぬ事だ。
君は理屈ではなんら恥ずべき事がないと思っている。しかし実際では決してそうは行かない。芸術の神聖を信じ、芸術が実生活の上に玉座を占むべきものであるのを疑わない君も、その事がらが君自身に関係して来ると、思わず知らず足もとがぐらついて来るのだ。
「おれが芸術家でありうる自信さえできれば、おれは一刻の躊躇もなく実生活を踏みにじっても、親しいものを犠牲にしても、歩み出す方向に歩み出すのだが…家の者どもの実生活の真剣さを見ると、おれは自分の天才をそうやすやすと信ずる事ができなくなってしまうんだ。おれのようなものをかいていながら彼らに芸術家顔をする事が恐ろしいばかりでなく、僭越な事に考えられる。おれはこんな自分が恨めしい、そして恐ろしい。みんなはあれほど心から満足して今日今日を暮らしているのに、おれだけはまるで陰謀でもたくらんでいるように始終暗い心をしていなければならないのだ。どうすればこの苦しさこのさびしさから救われるのだろう」
…
う〜ん
なんてすごい文章でしょうか
よくよく有島の生真面目で律儀な性格も
如実に垣間見れて
思わず感銘を受けた次第です
というわけで
有島武郎の『生れ出づる悩み』
今更ながら
これは優れた私小説
あらためてオススメです


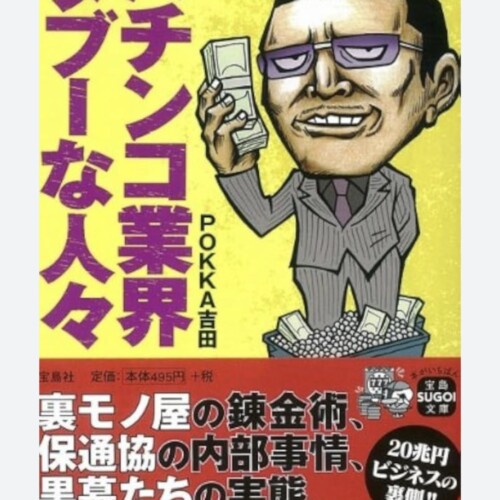
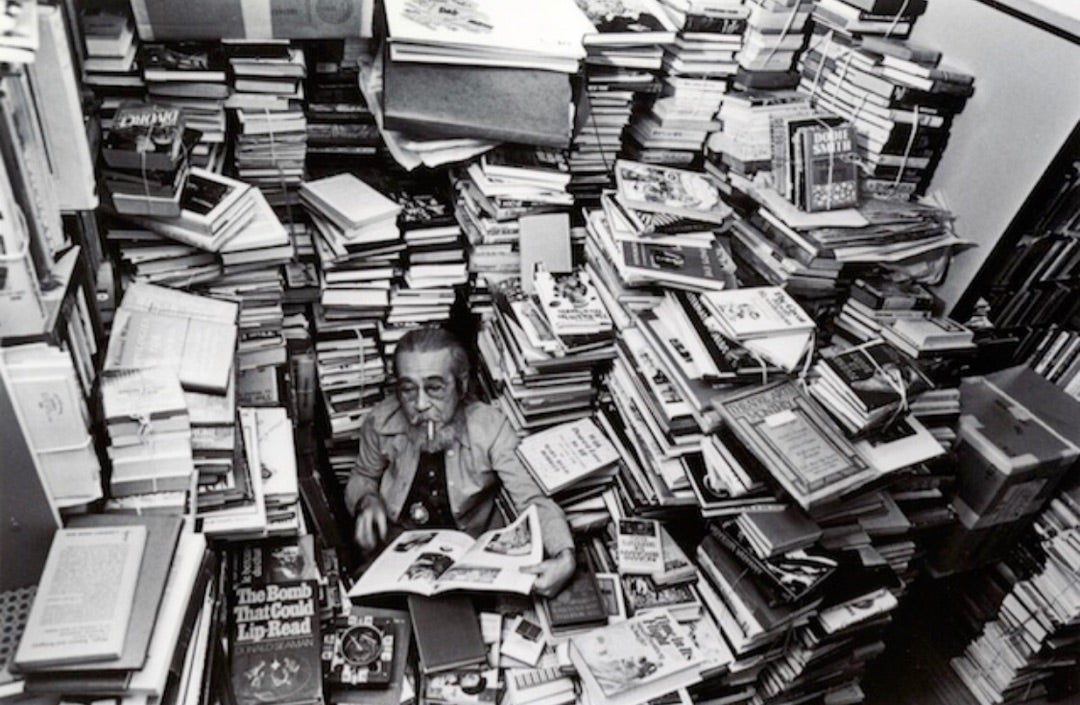
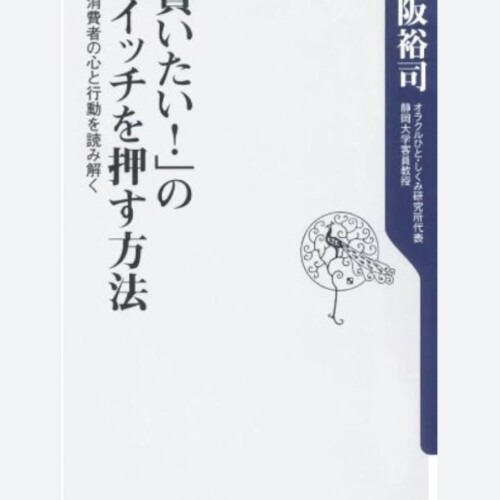
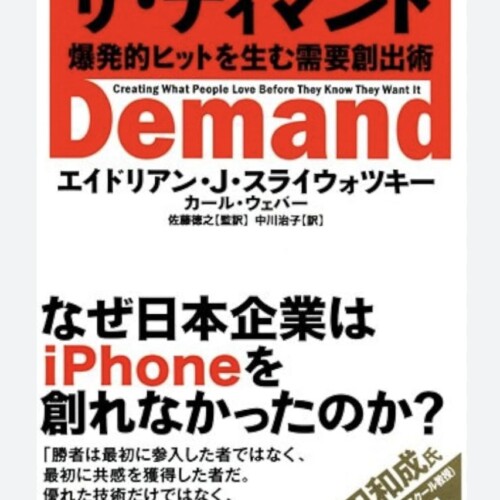
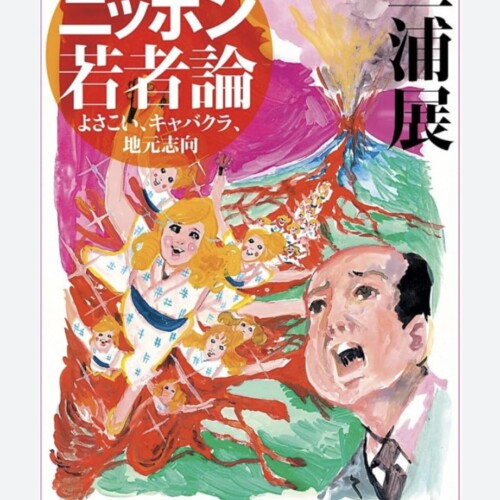
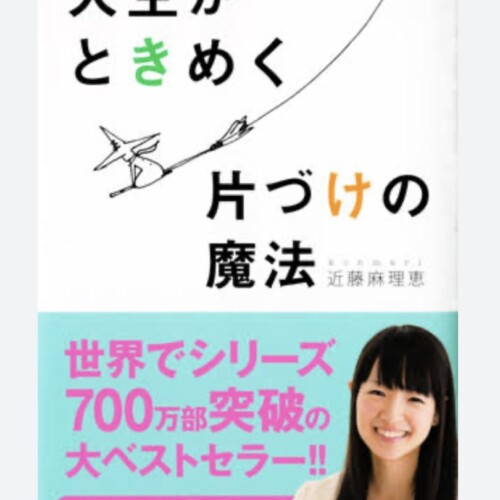
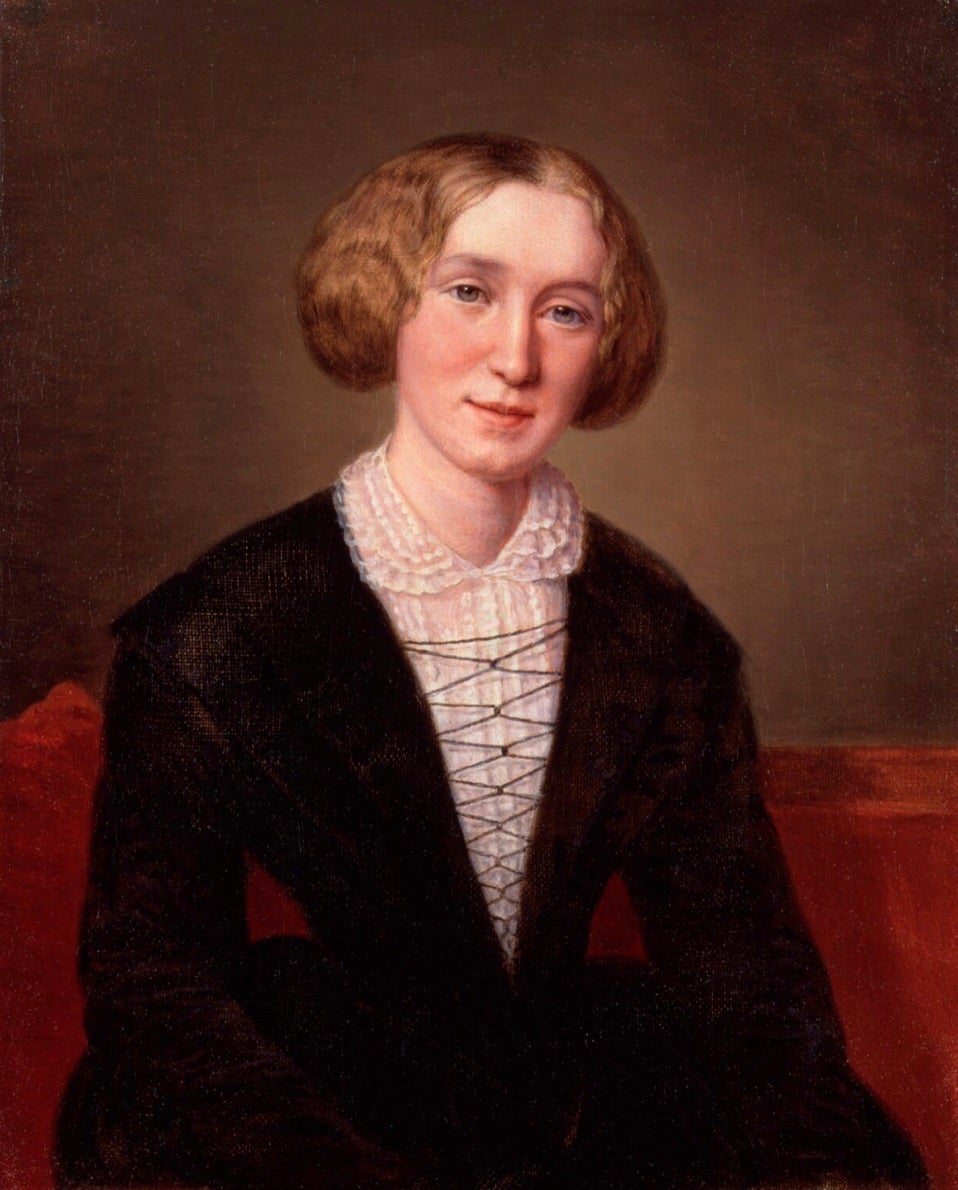
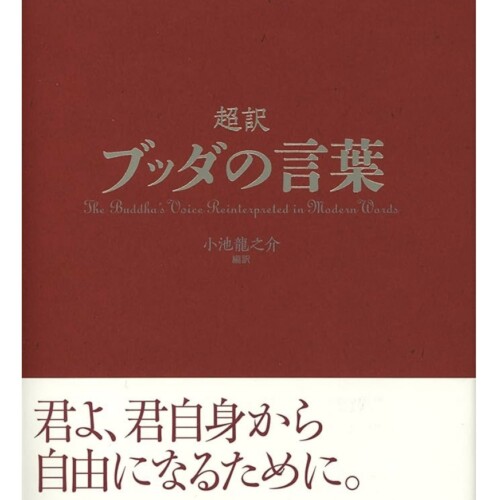
この記事へのコメントはありません。