映画『サテリコン』

1969年製作
イタリア・フランス合作の
『サテリコン』
↓↓↓
監督はご存じ
イタリアの巨匠
フェデリコ・フェリーニ(1920-1993)
↓↓↓
古代ローマの詩人ペトロニウスが
当時の有力者たちの退廃ぶりを記録したとされる紀元1世紀頃の文学を
“映像の魔術師”フェリーニが映画化
↓↓↓
って
本作は
フェリーニの豊穣なイマジネーションが
自身のキャリアの中で
最も過激で奇怪で
いわばグロの方向に拠った映画で
まあこれは色彩感覚といい
70年代というサイケな時代性が多分に色濃く反映され
当時の狂騒と絶妙にマッチした産物といえましょうか
『カサノバ』(1976)も大概でしたが
↓↓↓
本作においてフェリーニは
古代ローマという時代設定を借りて
いやあ
文字通り、己の感性を爆発させます
倫理やタブーが形成される以前の
原初の古代世界を自由奔放な解釈で映像化します
↓↓↓
と
フェリーニとともにイタリア映画黄金期を担った
ルキノ・ヴィスコンティは
同じ年の1969年に
『地獄に堕ちた勇者ども』を発表
↓↓↓
こちらも強烈で
スタイルも作風も違えど
それぞれがクリエイターとしての鋭敏な感性をもって
70年代というカウンターカルチャーが吹き荒れた時代の
ある種の毒
退廃的なムードを
ビビッドに表現した結果といえましょうか
巨匠2人の対比が面白いですね
そんなわけでして
本作『サテリコン』は
キリスト教が普及する以前の古代ローマを舞台に
青年エンコルピオが辿る数奇な冒険譚です
↓↓↓
美少年ジトーネを親友アシルトに奪われ
大地震に見舞われ
大富豪トルマキオの大饗宴に足を踏み入れ
船へと連行され
そうした様々な紆余曲折を経て
やがて自由の身となる…
特筆すべきは
次々と目の前に現出される
不気味で幻惑に満ちたスペクタクル的な世界です
↓↓↓
ローマ郊外の撮影所チネチッタで作られた
CGに依拠すべくもない壮大なセットの数々
↓↓↓
観る者を圧倒してやまない異様な造形美術
↓↓↓
グロテスクな仮面
際立つ卑猥なキャラ
↓↓↓
厚化粧を施し
↓↓↓
奇抜な衣装に身を包んだ彩り豊かな人物たち
↓↓↓
イタリアを代表するバロックの画家
カラヴァッジョの絵画の中の人物を彷彿とさせますね
↓↓↓
う〜ん
この得も言われぬ高揚
この不気味で特異な世界観に
正直ゾクゾクする僕がいます
↓↓↓
(ええっ)
キリスト教による価値観が浸透する前の
退廃の極みにあった古代ローマ
混浴の大浴場、娼宿など、見世物小屋的な風情をたたえながら
そこに集う人々の
いわば欲望の塊がどんどんと肥大し
やがて巨大なエネルギーとなって画面全体に充満
延々繰り広げられるトルマキオの饗宴
飲んで喰らい歌い踊り交わり…
その酒池肉林の異様
↓↓↓
そこに様式的な秩序はない
映画はおよそ収束の道筋も
結末の予想もつかない迷宮を延々さまよいながら
倫理も
道徳も
性の垣根も
軽々と飛び越え
感情がほとばしり生命が横溢する様を
古代ローマという
堕落と放蕩の極みに達した魔界を舞台に
過剰なまでのイマジネーションで描ききります
↓↓↓
ふと
しかしそこにフェリーニ特有の
人工的な美しさが垣間見れ…
なんといいますか
観ていて
時折ハッとさせられるんですよね
驚異の映像美といったら陳腐に聞こえますが
つくづく
フェリーニの映像って
独特の艶があります
とりわけ本作は
カラフルな色彩による古代世界の描写が
多分にサイケなムードを醸成
↓↓↓
いまだかつて観たこともない
未曾有のスケールをもって
豪華絢爛で
それでいておぞましい世界が
縦横無尽に展開されていきます
↓↓↓
フェリーニとの名コンビで知られる
ニーノ・ロータの音楽も欠かすことができませんね
本作のキッチュで幻想的な世界観を
異質で斬新な音を織り交ぜながら
効果的に表現しています
前回ご紹介の
第三世界的なローカリズム漂うパラジャーノフの映画も
また古代世界を独自の解釈で再創造したパゾリーニの映画もそうですが
つくづく
僕はこういう映画が好きなんですよね
いやあ
しっかし
なんとまあパワフルでエネルギーに満ち溢れた映像表現でしょうか
というわけで
フェリーニが渾身の力で放った怪作
『サテリコン』
正直
好き嫌いははっきり分かれるでしょうが
僕はまぎれもない傑作だと確信します
必見です


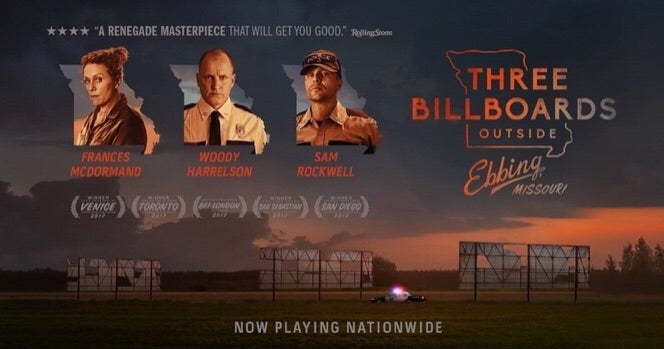
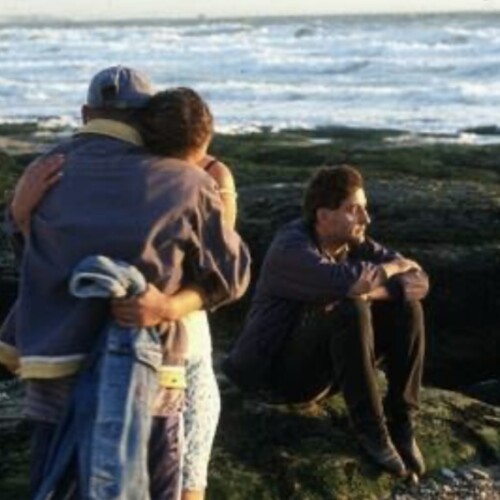






この記事へのコメントはありません。