映画『怒りの日』

映画評
1943年のデンマーク映画
『怒りの日』
↓↓↓
監督は
“デンマークの至宝”と謳われた世界的な巨匠
カール・テオドア・ドライヤー(1889-1968)
↓↓↓
原作は
ノルウェーの作家ハンス・ヴィアス=イェンセンの戯曲で
本戯曲は
16世紀に実際にあった事件を元にしていると言われています
とまあ
あらためて
本作のテーマは魔女狩りです
物語の舞台は中世のノルウェー
村の牧師アプサロンは以前に妻を亡くし
今は2番目の若い妻アンネと母親と3人で暮らしている
かつてアンネの母親が魔女として告発されるも
アプサロンの弁護で死を免れ
そうした縁でその娘を娶ったものの
母は若いアンネに自分の息子を奪われたとして
アンネを疎ましく思っている
そんなある日
アプサロンの一人息子マーティンが帰郷する
歳が近いアンネとマーティンは互いに惹かれ合い
逢瀬を重ねるうちに
↓↓↓
やがて愛し合う関係となってしまう
↓↓↓
かねてより
歳の離れた夫に不満を抱いていたアンネは
次第にマーティンへの情熱と欲望をあらわにし
↓↓↓
ある夜
とうとうアプサロンに
本心の一端を吐露してしまう
↓↓↓
それを聞いたアプサロンは
ショックのあまり急死…
するとにわかに
「アンネは魔女だ」
「彼女の呪いがアプサロンを死に至らしめた」
との告発が起きる…
↓↓↓
う〜ん
怖い映画です
と
本作が決して単純な話ではない最大のポイント
それは
アプサロンが突然死したのは
妻と息子の不貞を知ったことによるショック死によるものなのか
それとも本当に魔女の呪いによるものなのか
…を演出上
意図的に曖昧にしている点にあります
本作が戦前というだいぶ古い時代に製作されたとはいえ
観ている方はまさかアンネが本物の魔女なはずはないということを
重々承知しているはずです
魔女狩りは人間の偏見と不寛容がもたらした
旧時代におけるキリスト教の負の産物に他ならない、と
が
しかし本当にそうでしょうか?
ドライヤーはあえて従来の認識を覆す大胆な表現を試みることで
作品そのものに深みをもたらし
観る者に想像力という揺さぶりをかけていきます
息子のマーティンはアンネに想いを寄せるも
内心ではアンネが本当に魔女で
彼女がわが父を殺したのではないかと疑い悩みます
↓↓↓
と
愛するマーティンが自分に対して疑念を抱いていると察したアンネは
審問官から殺したのかどうかを問い詰められると
あえてそれを否定せず
「私が殺した」と認め
そうして映画は終わりを告げます
(おそらく彼女はこの後、火刑に処せられるのでしょう…)
よくよく
本作は
本質的には
純愛を描いた映画だと実感する一方で
しかし
つくづく
なんて言えばいいんでしょうか
物語が進行するにつれて
宗教的権威の犠牲者で
観る者の同情を誘うはずのアンネが
う〜ん
正直、どんどん悪い顔をしていくんですよね…
↓↓↓
序盤で見せる清楚な若妻ぶりのアンネと
帰郷したマーティンに対し恋の炎を燃やし始める中盤以降のアンネとでは
まるで別人のようです
ふと
アンネは本当に魔女なんじゃないかと
観ている方があらぬ疑惑を抱くほどです
アンネを演じるリベスト・モーヴィンの
挑発的な鋭い眼光がひときわ印象的で
いやはや
惑わされます
↓↓↓
ドライヤーは
アンネというキャラクターに
魔女的な要素を盛り込むことで
むしろそこに善悪を超えたところの
普遍性を見出そうとしました
そもそも本作が撮影された1943年のデンマークは
当時、ナチスの支配下にあって
ユダヤ人排斥が公然と横行していた時代
まさに魔女狩りはユダヤ人狩りのメタファーと捉えてしかるべきです
が
しかし本作はそれだけにとどまりません
映画は決して
安易に答えを提示するようなことはせず
観る者一人一人に委ねる形で
彼女の言動の是非を
さらには良心のありかを問いかけ
愛と信仰の意味
その宗教的な命題を
無言のうちに突きつけます
そして特筆すべきは
デンマークのプロテスタンティズムの厳格な精神が息づく
北欧神秘主義とリアリズムの
この奇跡的な融合です
光と影の強烈なコントラストによる緻密な空間設計
人間心理の闇の部分を炙り出すような透徹したリアリズム描写
つくづく
この全編を覆う
尋常ならざる異様な空気感…
まさに圧巻の一語です
禁断の物語が至高の領域へと昇華した
これは何よりの所以ですね
いやあ
この映画が80年近く前に作られたという事実に
まずもって驚かされますね
というわけで
『怒りの日』
ドライヤーの底知れぬ才能が爆発した
まこと恐るべき傑作です








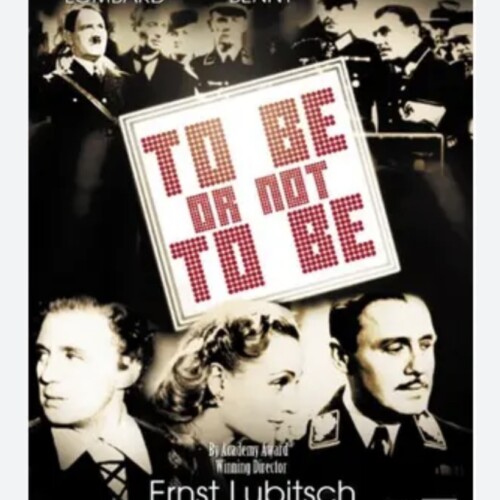

この記事へのコメントはありません。