映画『雨のしのび逢い』

1960年製作
フランス、イタリア合作の
『雨のしのび逢い』
↓↓↓
監督は
イギリス演劇界の生きる伝説として知られる
ピーター・ブルック(1925-)
↓↓↓
彼は数々の舞台演出で名を馳せる一方
若い頃には優れた映画も数本、監督しています
本作は
ブルックの演劇的な発想と
そして原作者で脚本も手がけた
マルグリット・デュラス(1914-1996)の
前衛文学的なスタイルが奇妙に相まった異色作です
↓↓↓
フランス西海岸の田舎町
製鉄所長の妻アンヌは
息子のピアノのレッスンの最中に
周囲一帯に響くような
女の鋭い悲鳴を耳にする
警官や群衆に囲まれた現場の酒場へ行ってみると
女が床に倒れていて
↓↓↓
死んでいる女を
犯人の男が執拗に愛撫しているのを
警官が無理やり引き剥がそうとしていた
↓↓↓
どうやら痴話喧嘩の果ての殺人だったようだ
が
その光景を目撃したアンナは
衝撃にとらわれる
↓↓↓
犯人の男が見せた
相手を殺すほどの激しい愛情は
何不自由ない裕福な生活ながら
夫との冷めきった関係が長年続いている彼女にとって
少なからぬ啓示を与えた
翌日、殺人現場の酒場でアンヌは
鉄工所の工員ショーヴァンに声をかけられ
↓↓↓
昨日の事件について話し合ううちに
2人は毎日、逢瀬を重ねるようになる…
↓↓↓
う〜ん
意識の変容は
日常において
不意にやってくる
激しい衝動に突き動かされた男の犯行を
目の当たりにしたアンヌは
そうした感情が失われて久しい
自身の空虚な日常を
つかの間
顧みるきっかけとなり
そうした思いに日々囚われ
心掻きむしられます…
↓↓↓
つくづく
本作の中では
彼女の中で一体何が起きているのか?
余計な説明は排され
あくまで状況描写のみで
よくわからない
しかし
わからないけど
わかる
実際のところ
彼女の心情
その本質的な危機感が
観ていて痛いほど伝わってきます
↓↓↓
彼女を取り巻く窮屈な日常
将来に対する
漠然とした
しかし
確かな不安…
ふと
アントニオーニの“愛の不毛“
ともまた違った
画面全体を覆う虚無感
観念的なまでの不安感
まあ文学的ではありますね
彼女が不安を抱く理由や出来事など
具体的な説明や描写は一切なされませんが
主演は
かのジャンヌ・モローです
その苦悩に満ちた内面
揺れ動く感情が
まこと的確に表現され
リアルな説得力を観る者にもたらしています
↓↓↓
また相手役にジャン=ポール・ベルモンド
男の素性や真意などが
これまたはっきりしない役どころで
意味深長なセリフと
悠然とした佇まいが印象的ですね
↓↓↓
と
2人は互いに思いを寄せ合い
愛し合うようになるのですが
劇中ではキスシーンもなく
どこまでも暗喩的な表現にとどめられます
↓↓↓
心のモヤモヤが晴れないアンヌは
さきの情痴殺人の意味を
自身に問い
どこか疑似体験を求めていたのでしょうか
ショーヴァンから放たれた思わぬ言葉に
絶望の悲鳴を上げます
↓↓↓
その後
何事もなかったかのように
夫の車に乗り
帰宅して
映画は唐突に終わりを告げるのです…
う〜ん
表面的には
彼女には何も起こっていない
曇天の空の下
退屈な日常が続くのみ
しかし彼女の中では
心の叫びがこだまし
おそらく
もはや元には戻らないだろう
と
まさに
本作の特異な点はここにあります
何も起きない
…が
内面は激しくうごめき
やがては心の破滅をもたらす
そうした結末と
そこへ至るプロセスが
まこと象徴的に表現されているのです
これで映画を成立させちゃうんですから
つくづく
ブルックの監督としての力量には
感嘆の念を覚えますね
って
よくよく
雲をつかむように曖昧で難解な役を
見事演じきったジャンヌ・モローが
なんといっても素晴らしいですね
というわけで
『雨のしのび逢い』
デュラスの愛の深淵
ピーター・ブルックの卓越した手腕によって創出された
ミニマムで特異な世界観
いやあ
今更ながら傑作です
おまけ
演出風景です
↓↓↓








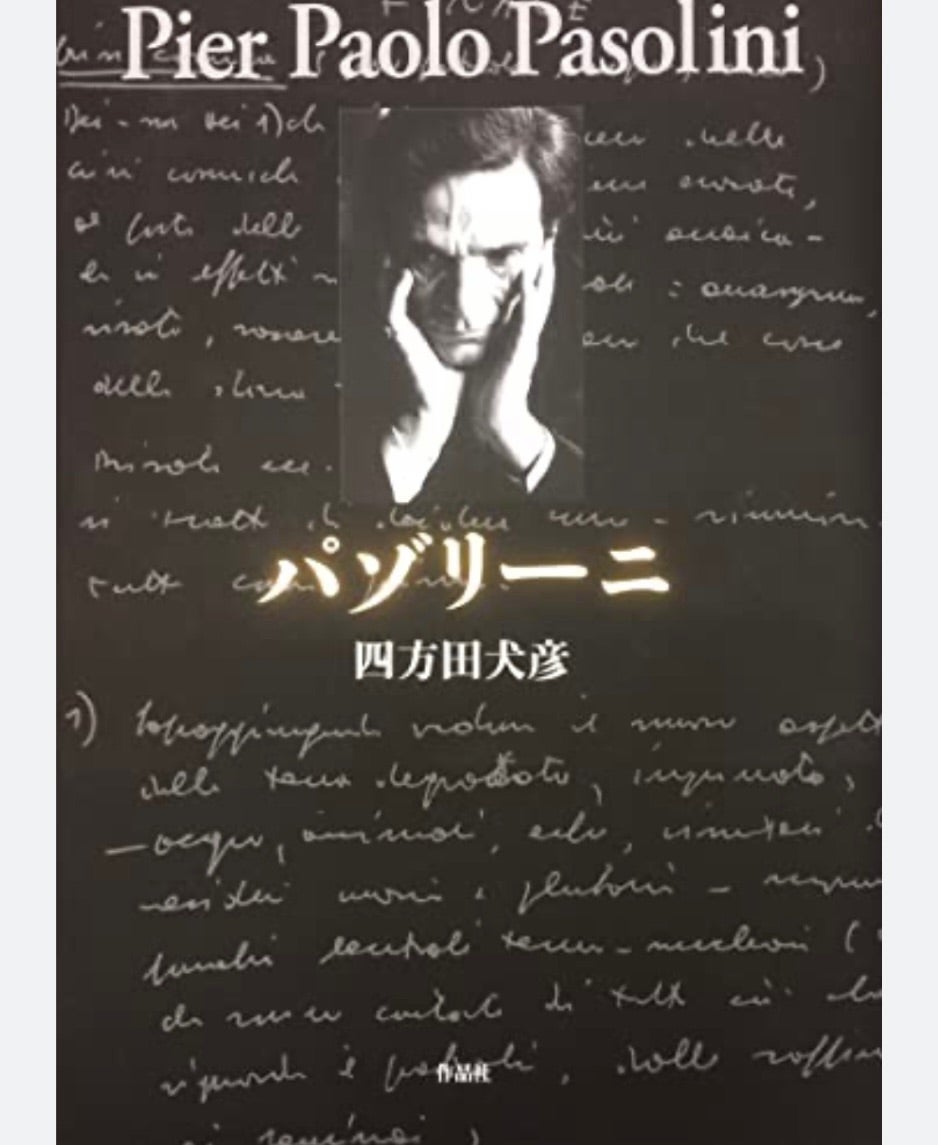

この記事へのコメントはありません。