映画『牯嶺街少年殺人事件』
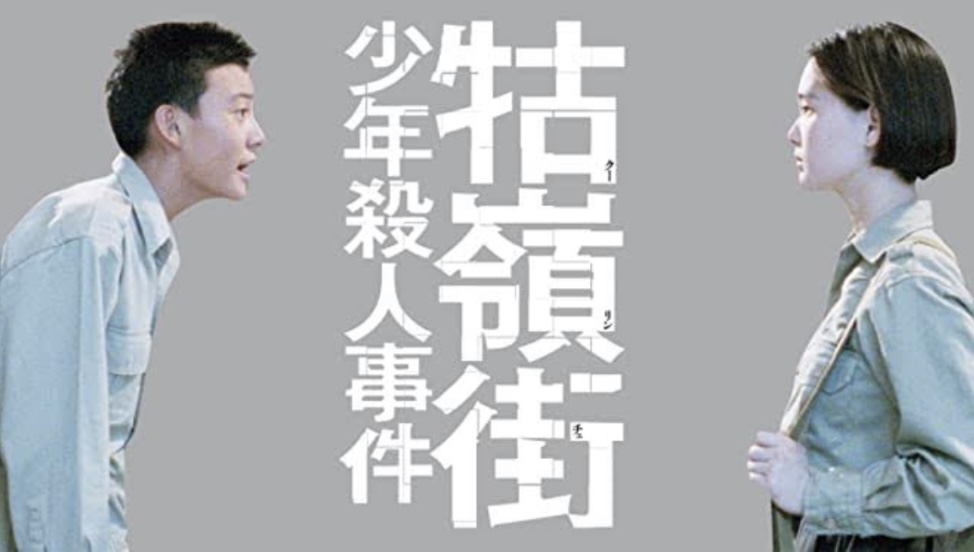
何かと映画づいている今日この頃
待望の再鑑賞が実現
1991年製作の台湾映画
『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』
↓↓↓
公式サイトは→こちら
長年、DVD化も叶わなかったこの伝説の傑作が
この度4Kレストア・デジタルリマスター版として
25年ぶりに再上映が実現したのですから
これは何はさておいても観に行かないわけにはいきません
監督は59歳で惜しくもこの世を去った
台湾が誇る天才
エドワード・ヤン(=楊徳昌、1947-2007)
↓↓↓
やはり近年、再上映が果たされたヤンの傑作
『恐怖分子』について
僕が以前書いたブログは→こちら
本作『牯嶺街少年殺人事件』は
上映時間が実に3時間56分という長尺
しかし終始圧倒されっぱなしの
それでいて至福のひと時でしたね
この映画は1961年に実際に台北で起こった
中学生男子による同級生女子殺傷事件がモチーフとなっていて
悲劇の結末に至った経緯を
対立する不良グループの少年たちとその家族の日常を丹念に紡ぎ出すことで
当時の台湾が抱えていた矛盾や精神的危機感を
鮮烈に炙り出してみせます
↓↓↓
1960年代初頭の台北
建国高校夜間部に通うシャオスーは
自然の成り行きから
不良グループ“小公園”の仲間たちとつるんでいた
シャオスーはある日
保健室でシャオミンと知り合い
やがてほのかに恋心を抱く
↓↓↓
しかしシャオミンの恋人で
“小公園”のボス
ハニーが帰ってきたあたりから
↓↓↓
対立するグループ“217”との抗争が激しさを増し
シャオスーやシャオミンたちは
次第にその渦の中に巻き込まれていく…
↓↓↓
と
物語の時代背景として
押さえておかなくてはならない歴史的経緯を少々…
長年、日本の植民地だった台湾は
1945年に日本が敗戦国になったことによって
中国(国民党政府)に接収されるも
その後すぐさま共産党と国共内戦に突入し
結果、1949年に国民党政府は敗れてしまいます
そうした中で台湾には
国民党政府と共に撤退するように大陸から移り住んだ外省人と
接収以前からずっと住み続けている内省人という
イデオロギーも価値観も違う二者が対立し合いながらも共存する
特殊な社会環境が形成されます
映画はそんな時代背景を生きる
主には外省人たちにスポットを当て
彼らのアイデンティティの喪失を象徴的に描写していきます
中国共産党との関係を疑われ
厳しい取り調べを受ける主人公シャオスーの父
いずれは大陸へ帰ることを夢見ていた外省人たちですが
時が経つにつれ
やがてその夢を諦めるに至ります
ふと、こうしたくだりは
戦前に日本に渡り定住するに至った
在日一世の歴史や経緯を
自ずと連想させる話であり
う~ん
つい自分事として観てしまいましたね
そしてそんな外省人の親たちの不安感や苦悩を
無意識のうちに汲み取る
子供たちの危ういまでに繊細な感性と
突発的な衝動
やがて訪れる悲劇…
↓↓↓
主人公シャオスーと少女シャオミンのやりとりを
しばしば現場音が遮ります
時には
軍のヘリコプターのプロペラの音だったり
あるいは
学校での楽隊による演奏の音に
二人の声がかき消されたり…
↓↓↓
そうして終盤
少女シャオミンはシャオスーに語ります
「私を変えたいのね
でもこの社会と同じ
何も変わらないのよ」
対立するグループ間の生々しい諍い
プレスリーを夢見る少年の甘い歌声
軍人や戦車の存在など戒厳令下にある日常
古い日本家屋の情緒
酔ってクダをまく隣人…
積み重ねられたショットの鮮烈な断片
映画は歴史の大きなうねりの中でもがく
少年少女たちの素朴で悲痛なまでの声と狂おしいほどの激情を
緻密な空間設計に基づく遠近法を多用した張り詰めた画面構成
効果的な現場音を多用した音響など
様々な技法を駆使して余すことなく捉えています
いやあ
和洋中が絶妙にコンデンスした60年代台湾の
なんとまあ
豊穣なまでの世界観でしょうか
まさに小さな物語の中に世界を見る
閉塞した今を生きる少年少女たちとその家族の
光と影を映し出すことによって
世界を再構築しようと試みた
このとてつもないスケール
つくづくエドワード・ヤン恐るべし
あらためて本作はアジアが世界に誇る
まこと稀有な傑作です


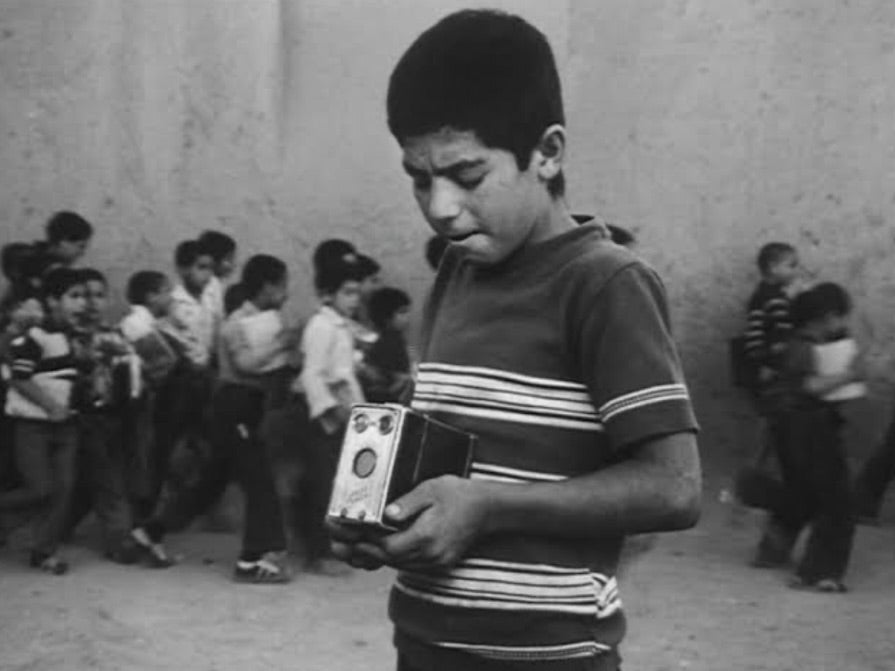


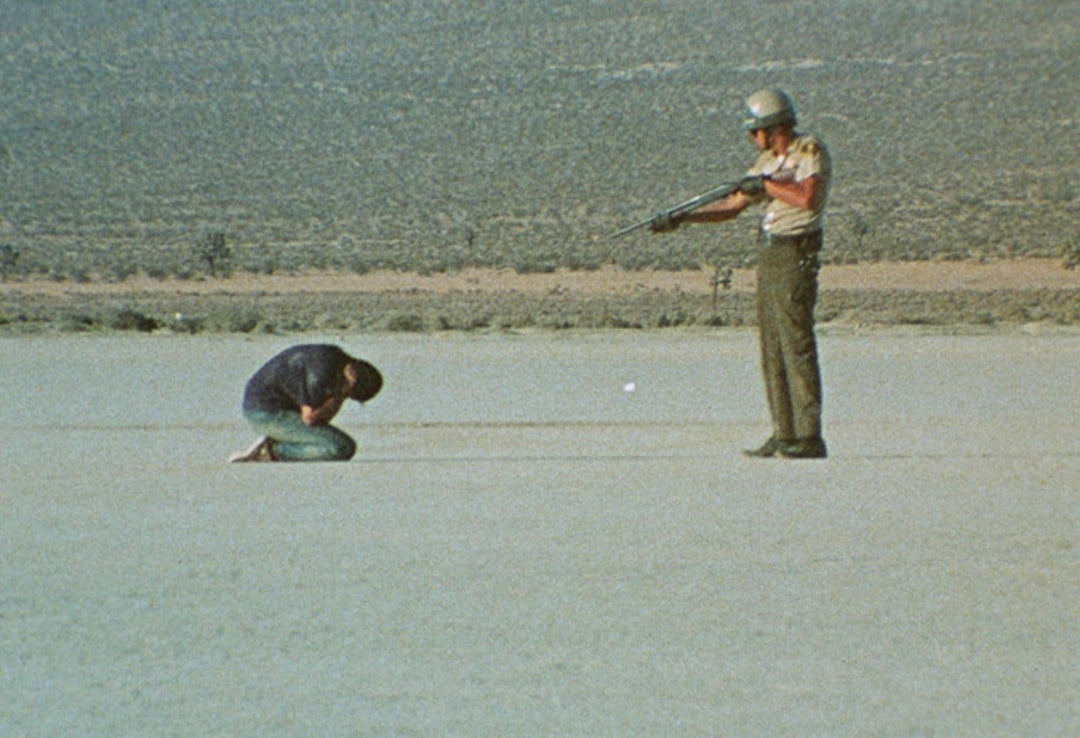


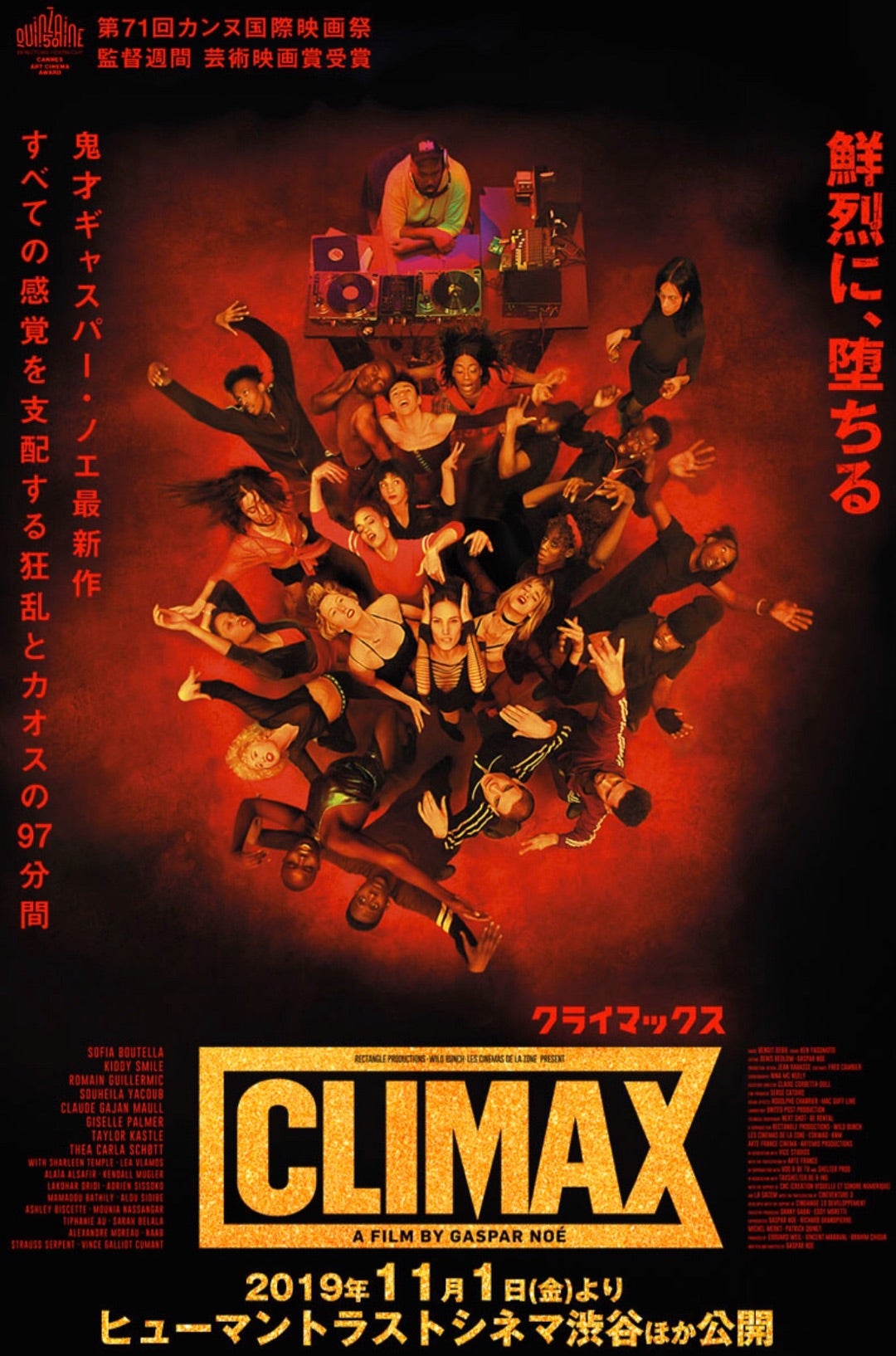
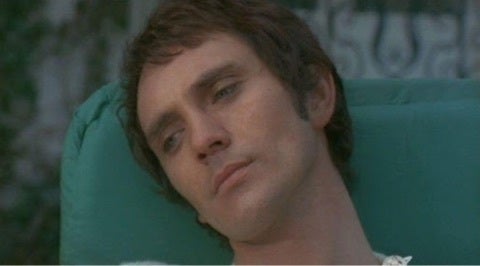
この記事へのコメントはありません。