映画『WANDA/ワンダ』

1970年製作のアメリカ映画
『WANDA/ワンダ』
↓↓↓
アメリカ社会の底辺をさまよう
あるひとりの女性の魂の軌跡
本作は
舞台で鳴らした女優
バーバラ・ローデン(1932-1980)が
その短い生涯で唯一
監督・脚本・主演を兼ねて
自主製作した映画で
ジョン・カサヴェテスに端を発する
アメリカ・インディペンデント映画に連なる
記念碑的作品として
さらには
当時珍しい女性監督作品として
異彩を放つも
う〜ん
しかし
長い間
闇に埋もれていた
幻の映画なのです
↓↓↓
バーバラ・ローデンは
『波止場』(1954)や『エデンの東』(1955)などで知られる
アメリカの巨匠エリア・カザン(1909-2003)の妻として
彼の作品ほか
映画や舞台に出演していましたが
年齢を重ねるにつれて
次第に女優としてのキャリアの限界や
自己のアイデンティティに直面し苦悩します
そんな中で
ある目に止まった新聞記事に着想を得て
夫のカザンの協力のもと
低予算の自主製作で完成させたのが本作です
って
ローデンは
1980年に乳がんにより
48歳の短い生涯を終えるのですが
まさに本作『WANDA/ワンダ』は
彼女の監督デビュー作にして遺作となったわけですね
と
本作は
1970年の第31回ヴェネツィア国際映画祭で最優秀外国映画賞を受賞し
1971年の第24回カンヌ国際映画祭でアメリカ映画として唯一上映された
…にもかかわらず
当時のアメリカ本国ではほぼ黙殺されます
しかし後に
世界の名だたる映画作家やアーティストから
「失われた傑作」と称賛されるようになり
2003年にオリジナルのネガプリントが発見
そして2010年に
かのマーティン・スコセッシ監督が設立した
ザ・フィルム・ファウンデーションと
GUCCIの支援でプリントが修復され
アメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録されるに至ります
そうして昨年
日本でも初めての劇場公開が叶ったという
いやあ
まさに数奇な運命を辿ったフィルムと言えましょうか
…
アメリカ、ペンシルバニア州の鉱山地帯
↓↓↓
炭鉱夫の夫と別れ、子の親権を奪われ、職を失い、有り金もすられ
途方に暮れ夜の街をさまようワンダは
バーで知り合った男デニスと行動を共にし
↓↓↓
やがて彼の犯罪に加担する…
↓↓↓
ふぅ
ワンダの遍歴…
ポツンとした郊外の売店で
ゆきずりの男の車からひとり降ろされ
しかたなく
アイスクリームを買う
ショッピングモール内をうろつき
ショーウィンドーを覗き込む
↓↓↓
何気なく入った映画館で
↓↓↓
バックを取られ財布のお金をすられる
やがて
犯罪者の男と知り合い
↓↓↓
彼の傲慢な態度に嫌気がさすも
共に逃避行を重ねる…
↓↓↓
つくづく
彼女が身にまとう
無力感、諦念、絶望
自ずと陥る
精神的な危機
そして孤独…
↓↓↓
映画は
1970年前後に撮影された
アメリカの地方都市の
ありのままの現実
その生々しくも乾いた空気感
尊厳を踏みにじられ
受動的にしか生きることができない
ひとりの女性の実存的なまでのありようを
ドキュメンタリータッチ
…というより
限りなくリアルが刻印された
ザラついた映像で描写していきます
↓↓↓
う〜ん
アマチュアの役者を使った
手持ちカメラによる即興的な演出が
観ていて
なんとも荒削りで
しかし
予測できない危うさ
緊張感をはらんでいて
思わず画面に釘付けになりますね
↓↓↓
ローデンは
主人公ワンダについて
「彼女はこのひどく醜い生活から抜け出そうとしているが、道具を持ち合わせていない」
と語っています
また本作は
フェミニズム映画の系譜で語られることが多いのですが
彼女は否定していて
本作について
「女性の解放ではなく、女性や人々に対する抑圧を描いた」
と語っています
↓↓↓
というわけで
『WANDA/ワンダ』
つくづく
伝説の映画
アメリカ・インディペンデント映画における
輝かしい1ページを刻む
バーバラ・ローデン渾身の一作
幻のロードムービーの傑作です
↓↓↓




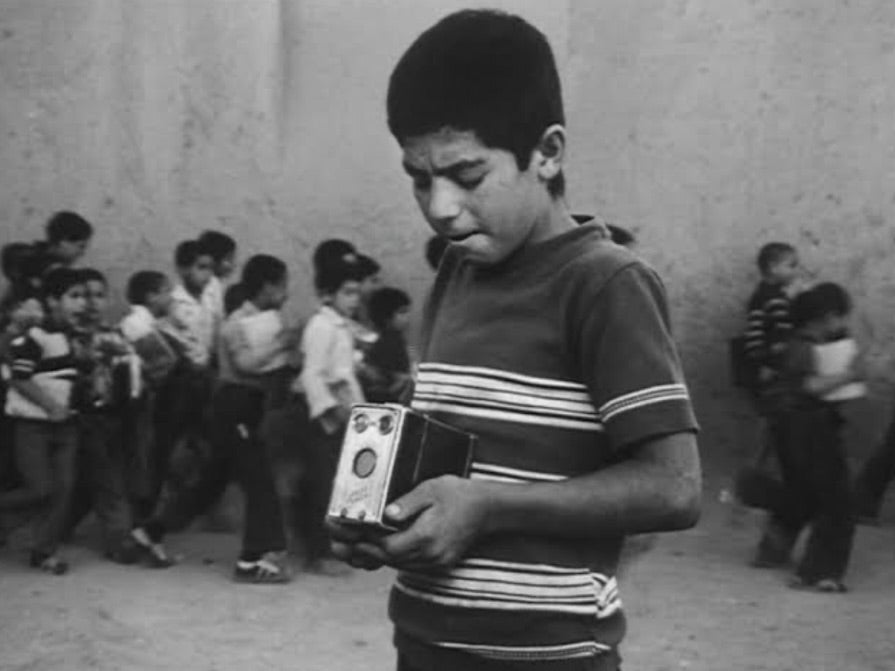

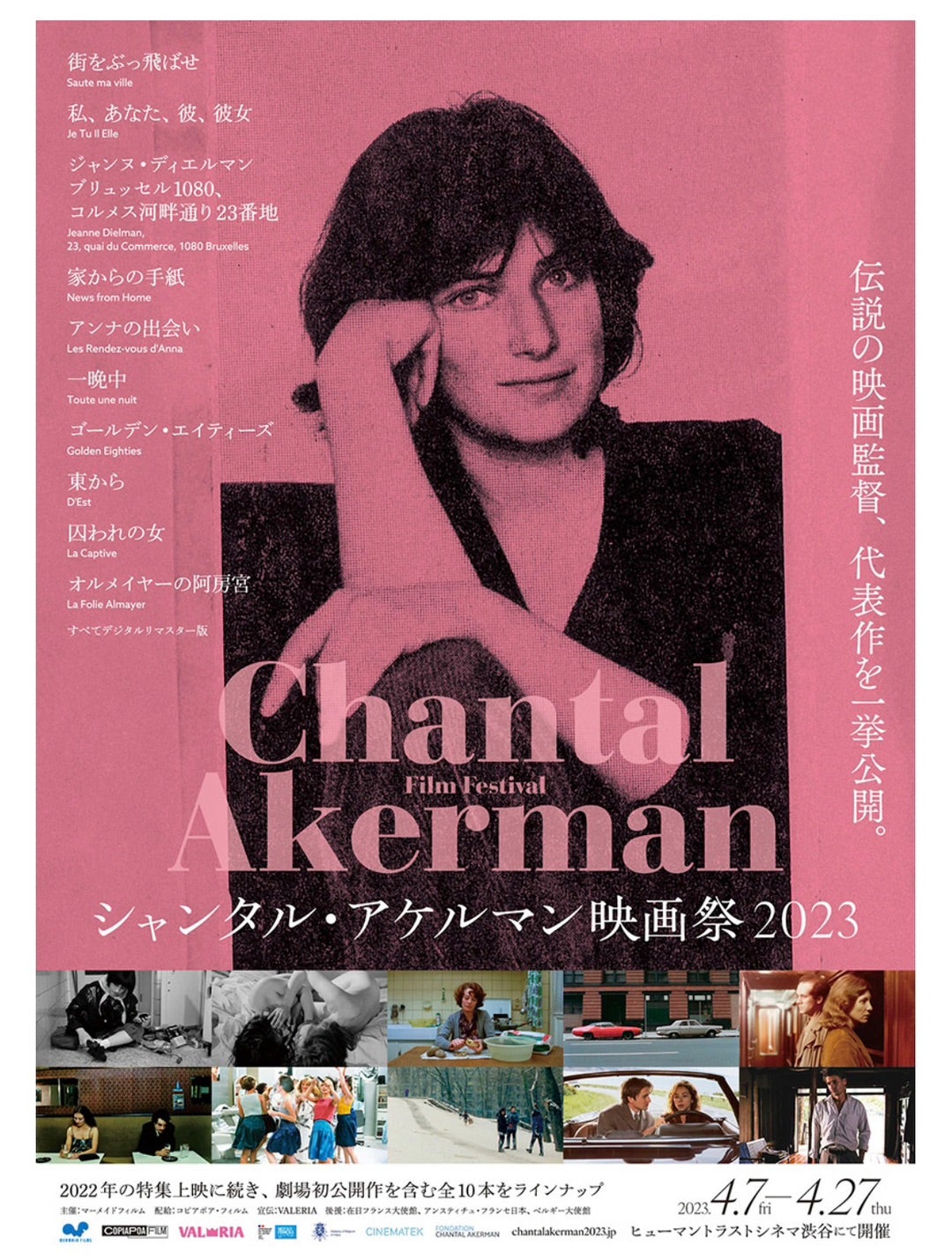
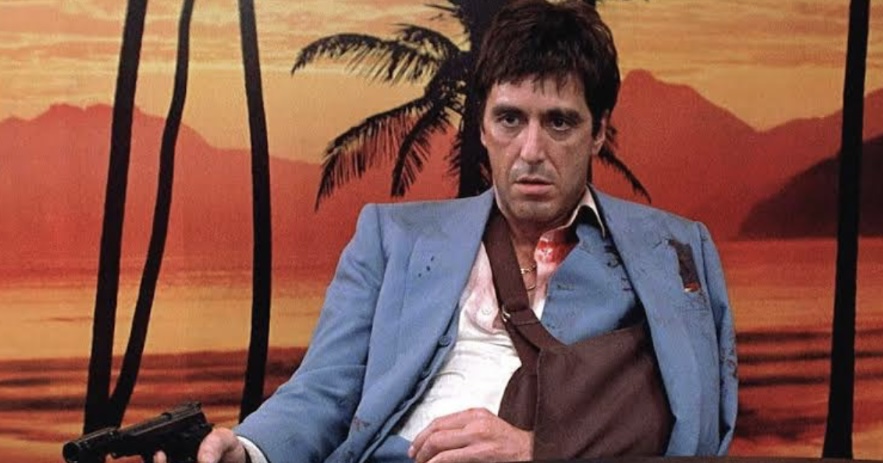

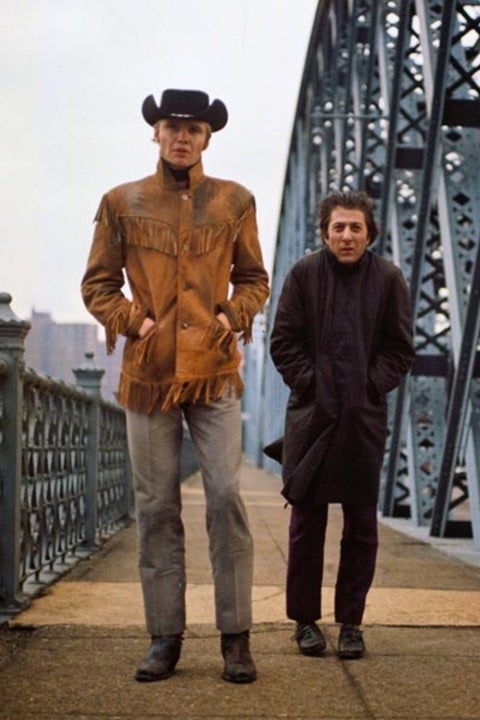
この記事へのコメントはありません。